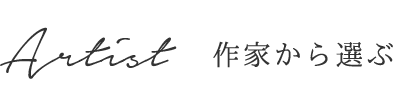淡い灰緑が美しい、市野耕さんの「彩色(さいしき)灰釉」のぐい呑み。
その時のインスピレーションで作られる酒器。
今回は呉須のブルーが美しい浅いタイプと、口元の輪花がとっても可愛らしいタイプ。
浅いタイプは径8.5cm・高さ3cmで、8分目の容量が50mlほど。
輪花のタイプは径7cm・高さ6cmで、8分目の容量が75mlほど。
ぐい吞みとしてのほか、豆皿や豆鉢としてお料理を盛っても、もちろん素敵です。
市野耕さんの「彩色灰釉」は、下地に白化粧(泥状の白い粘土)をかけ、そのうえから松の木の灰を調合した釉薬を施して作られるシリーズ。
化粧土の流れや、釉薬の濃淡で生まれる表情、そして釉だまりの「貫入」(かんにゅう・焼成の際の釉薬と土の収縮差によって釉薬表面にできるヒビ模様)など、彩り豊かな景色が楽しめるうつわです。
他にも、釉薬が薄い部分は焦げのような風合いだったり、土に含まれる鉄が表面に現れて黒点が見られたりと、見どころがたくさんです。
浅いタイプには結晶がよく見られ、輪花のタイプは特に見込みの釉だまりが美しいです。
裏側には、市野耕さんのサイン「k」が彫り入れてあります。